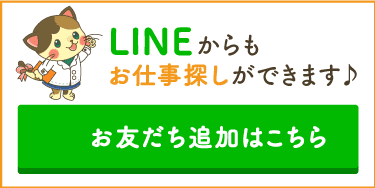特養・有料老人ホーム・グループホームなど、高齢者施設にはさまざまな形態があります。通称「老健(ろうけん)」と呼ばれる介護老人保健施設もそのひとつ。
老健は、入所者さんの在宅復帰が目的の施設です。医療ケアを行う医師や看護師・リハビリ職・介護職など多職種が働く施設で、多くの栄養士・管理栄養士が活躍する高齢者施設でもあります。
就職先・転職先の選択肢として検討している人にとっては「実際のところ老健で働くってどんな感じなの?」と気になるでしょう。
そこで、今回は現役で老健に勤務する管理栄養士の中田さん(仮名)に、老健での仕事内容ややりがいなどをインタビューしました。
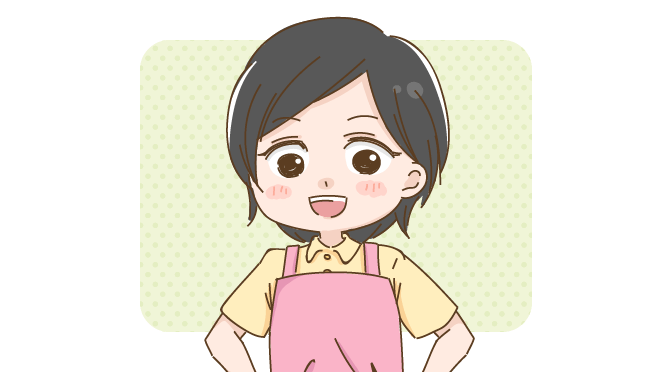
中田美貴さん(26歳・仮名)
大学卒業後、給食委託会社に勤務し老健に配属される。勤務歴4年目の管理栄養士。
目次
大学ではスポーツ栄養を研究!それがなぜ老健に就職?
―――現在は老健にお勤めの中田さんですが、管理栄養士を目指した理由は?
中田:もともと私はスポーツ栄養に興味があって、スポーツ栄養のことを調べているときに管理栄養士という職業に興味を持ちました。
あと私が通っていた高校では「テーマ研究」という授業があり、野菜が大好きだったことから、野菜の研究をテーマに栄養の話を調べていたら「栄養って面白い」と、栄養学にも興味を持ち始めて。
―――スポーツと野菜が管理栄養士を目指すきっかけになったんですね。
中田:そうです。食事って人間の一生に関わってくるし、絶対欠かせないものじゃないですか。なので、管理栄養士の資格を持っていたら仕事に困ることもないだろうし、幅広く仕事できそうだなと思ったのも、魅力を感じた理由でした。
―――意外なのが、中田さんは最初スポーツ栄養に興味があったんですよね? でも、そちらの分野には進まれなかった。
中田:確かに大学でもスポーツ栄養の研究は続けていました。でも結局委託会社に就職を決めたのは、一般的な栄養管理について学びたかったからです。
スポーツ栄養って、「競技で勝つための栄養」なので、健康を第一の目的とした栄養管理とは少し違って、独特なんですね。でも、この先ずっと管理栄養士を続けていくなら、やっぱり一般的な栄養管理を学んでおいた方が後々いろんな場所で活躍できそうだな、と考えまして。
それに「栄養士は現場経験があって一人前」という言葉を聞いたこともあったので、調理などの現場経験はしっかり積んでおこうと思いました。
―――なるほど。その目標を起点に就職先を決めたんですね。
中田:そうですね。現場経験を積みたいという目標があったので、色々な職場を経験できる委託会社に入社しました。そこで配属されたのが老健だったので、自分で選んだわけではないです。
管理業務がメインでもイベント食は自身で調理
―――4年同じ施設というと、それなりに長い印象ですね。業務の流れは完璧につかんでいると思うんですが、1日の動きってどんな感じですか?
中田:こんな感じのスケジュールになっています。
| 8:50 | 朝礼 |
| 9:00~9:30 | 厨房で前日の「申し送り」、食数の調整、食札の整理、栄養補助食品の補充 |
| 9:30~10:45 | 施設の事務所で献立作成、おやつの発注 |
| 10:45~11:30 | 入所者の昼食点検 |
| 11:30~12:00 | デイケアの昼食準備手伝い、点検 |
| 12:00~12:30 | ミールラウンド |
| 13:00~14:00 | 休憩 |
| 14:00~15:00 | ケアカンファレンス参加 |
| 15:00~16:30 | 栄養ケアプラン作成、入所の準備、ケアカンファレンス資料の準備、その他事務作業など |
| 16:30~17:30 | 入所者の夕食点検、翌日のデイケア食札準備、食数入力など |
| 17:40 | 退勤 |
―――中田さんの職場では、デイケア(通所リハビリテーション)も提供しているんですね。
中田:はい。献立内容は入所者も通所者さんも同じですが、食材の大きさや種類、調理方法は分けています。
―――その献立ですが、1日のスケジュールを見る限り、現在は調理業務は担当外なんですか?
中田:以前は調理業務もやっていたんですが、今は立場も変わったので、調理は厨房の調理師さんが行っています。高齢者向きに食材を軟らかくするための特殊な調理方法や食材の選定などは、調理師さんと相談しながら一緒に行っています。
―――こう見ると、中田さんの業務は献立作成や食事の点検、事務作業など「管理」的なポジションの人が行うものがメインなのかなと思いました。
中田:そうですね。今の私の役割は厨房で作業をすることよりも、調理師さんたちが作ったものを確認するとか、入所者さんたちの栄養管理や指導の内容を考えるとか、そういう業務の方が多いです。
でも完全に調理をする機会がなくなったわけではないですよ。うちの施設では行事や季節にちなんだ食事や施設の行事に沿った「イベント食」を月1で提供しているんですが、イベント食で提供するソフト食の調理は私が担当しています。
在宅復帰を目指す老健では、リハビリ職との連携が欠かせない
―――ケアカンファレンスは、他の職種のスタッフも参加するんですよね?
中田:そうですね。ケアマネージャーさんを中心に、介護士・看護師・薬剤師・理学療法士・言語聴覚士・作業療法士など、様々な職種のスタッフが参加します。
ケアカンファレンスでは、在宅復帰などを目的に、またご本人やご家族の希望に沿うために、入所者さんが施設でどのように過ごしていくか、身体機能改善のために何をするかなど、課題・目標・ケア内容について話し合います。
―――多くのスタッフが関わっているようですが、他職種同士で連携する場面って多いですか?
中田:多いです! 全部署が関わり合っているので、介護士・看護師・薬剤師・理学療法士・言語聴覚士・作業療法士さんたちとは、日常的な情報共有は密に行うようにしています。
利用者さんの食事の様子について介護士さんから「むせこみがあるので食事形態が合っていないかも」という相談を受けたり、フロアを見回っている看護師さんから「△△さんがどうしても食べられないらしいので、食べられるように手伝ってほしい」という依頼を受けたりすることもあります。
リハビリ職の方々には「リハビリ中の世間話のなかで、食事のこともぜひ聞いてみてくださいね」と言っているので、リハビリのときにそういう話が出たら共有してもらうこともあります。
―――老健は在宅復帰を目指す施設としてリハビリは重視していると思いますが、リハビリ職の方々とも協働は多いのでは?
中田:はい。摂食嚥下機能や食事動作に関わる運動機能の維持や改善には力を入れています。
なのでリハビリ職の方々、特に言語聴覚士さんとの連携は欠かせないですね。その入所者さんにとって最適な食事形態を考えるときとか、言語聴覚士さんと一緒に相談する場面は多いです。
―――なかなか大変そうですね……。お休みに関してはいかがでしょうか?
中田:毎月の休みは8日間あって、そこに有給休暇と季節休暇も加えると、年間で110日前後はあります。
―――長期休暇は取れる環境ですか?
中田:施設にもよりますが、私の場合は施設の管理栄養士が一人だけなので、連休となると難しいですね……。
一度だけ連休を取ったこともあるのですが、その時は施設や厨房からいつ連絡が来ても良いようにスマホを気にしてました。特に食事提供の時間前後は気が気でなくて……。
高齢者施設の食事提供で最も大切なのは「まずは食べてもらうこと」
―――大学在学中は高齢者施設での仕事に必要なことなど勉強する機会は少なかったと思いますが、実際に就職してみてギャップを感じたことってありましたか?
中田:管理栄養士というと、栄養管理や献立作成が主な業務と思っていたんですけど、「まずは食べてもらう(栄養を体に取り込む)ための工夫」がとても重要ということが、実際に仕事をしてわかったことでした。
―――「まずは食べてもらうための工夫」ですか?
中田:入所者さんに食べるための身体的・精神的な機能があれば問題ないのですが、うつなどの精神疾患や認知機能の低下で食べることがわからなかったり、集中力が続かなかったりする方々に食べてもらうのって、一筋縄ではいかないんです。
だからといって、病院のように栄養を点滴で入れることはできないので、「どうしたら口から食べてくれるのかな?」という課題には向き合わざるを得なかったというか。
栄養管理をするにも、まずは食べてもらわないと始まらないので、口から食べてもらう方法を考えることが、こんなに重要だったとは思っていませんでした。
―――口から食べてもらうために、どのような工夫をしていますか?
中田:食事の環境づくりや食事形態の考案、入所者さんへの声かけなど、ですね。とくに入所者さんとのコミュニケーションに関わってくる部分は重要です。
たとえば、入所者さんに初めて声かけをする前はその人の性格や持病などが記載されている紙面情報をよく読んで、ある程度どんな人物なのか把握してから臨むようにしています。
入所者さんに声かけするのは食事の時間が多いんですが、席の場所によってはゆっくり話ができない場合もあるので、そういうときはお部屋に伺います。
―――声かけにあたってベストなタイミングや場所を見極めていらっしゃるんですね。
中田:あと意外に重要なのが、声かけしたい入所者さんの周囲に座っている人たちの性格も把握しておくことですね。入所者さんにだけ用事があっても、周囲の人が食事の時間に話しかけにこられることを嫌がることもあるので。
―――なるほど。入所者さんたちの人間関係の全体図なども把握しておくことも、コミュニケーションをスムーズに行うために必要ということですか。
中田:はい。あと細かいところで言えば、食事って見た目がよくないとなかなか手が伸びないので、見た目には気を遣っています。特にイベント食の献立内容は、見た目にこだわるように意識していますね。
―――そういった細かい部分での工夫も、すべては「口から食べてもらう」ためのものなんですね。
中田:老健に限らずですが、高齢者施設での食事提供は「まずは食べてもらう工夫」を意識した工夫を行うことがポイントだと思います。
ベテラン言語聴覚士と二人三脚で試行錯誤
―――もともとはスポーツ栄養を勉強していたということなので、分野の違う高齢者の栄養管理の道に進んで「勉強しなきゃ」と思ったこともあるのでは?
中田:そうですね。身につけたいと思っていた栄養管理の知識に関しては、まず施設の管理栄養士が私ひとりという状況だったので、教えてくれる人もおらず……何もわからない状態だったので、自力でなんとか学ぶ必要がありました。セミナーや研修会には片っ端から参加したり、本を買ったり、病院に勤めている管理栄養士の友達に聞いたり。
あとは、食事形態の知識もきちんと身に着けなきゃなと焦りました。
―――確かに、食事形態は高齢者施設で働く人にとっては重要なポイントでしょうね。そっちはどんなふうに勉強していったんですか?
中田:たまたまだったんですが、私が管理栄養士として出向することが決まった直後にベテランの言語聴覚士さんが入職して、その方に教えて頂きました。
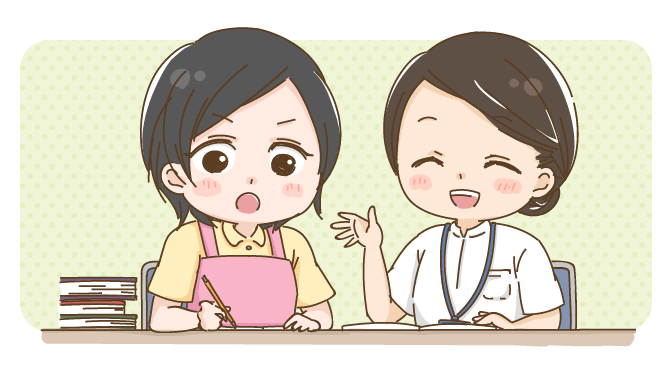
―――さきほどリハビリ職の方々には食事形態の相談をしていると仰っていましたが、その言語聴覚士さんは重要な協働者でしょうか。
中田:まさにそうです。言語聴覚士って言語に関するトレーニングだけではなく、摂食嚥下機能の維持や向上のリハビリもやるんですよ。摂食嚥下機能は食事形態と密接に関連しているので、そのあたりの知識も豊富なんです。
うちの施設の食事形態はあまり整っていなかったんですが、その言語聴覚士さんが入職したことで、改善していこうという話になりました。
なので私はその方にレクチャーを受けつつ、摂食嚥下機能をテーマにした日本歯科医師会主催の研修会に行ったり、本も見てみたりして、ふたりで試行錯誤し、施設の食事形態を考えていきましたね。
高齢者施設で働きたい人がもっていると良い意外な知識
―――管理栄養士を目指している学生さんのなかには、老健をはじめとする高齢者施設で働きたいという人も多いと思います。学生さんに、何かアドバイスはありますか?
中田:食事形態の勉強は、力を入れている学校が少ないと思います。今のうちから分かる範囲で勉強しておくと、後々ラクかもしれません。
持病を多く持っている入所者さんもいるので、疾患とか病気に関する知識も身につけておくと役立つと思いますよ。
あとは、仕事相手は全員年上なので、一般常識を身につけておくことも大切です。意外かもしれませんが、歴史の知識もあると結構役立ちます。
―――歴史の知識ですか?
中田:はい。結構な年齢を重ねている入所者さんだと、戦争を経験している人もいるので、ときどき会話の中で昔の戦争に関する話とか、何かしら歴史的なイベントや出来事に関連する話が出てくることもあるんです。なので、歴史を知っているとそのような経験をしている入所者さんに心を開いてもらうためのきっかけになると思います。
私は学生時代に世界史と中国語の授業を受けていました。その時の知識が、幼少期に満州で育ったという食欲不振の入所者さんと話すきっかけとなり、その後だんだんとごはんを食べてくれるようになりました。
高齢者施設に向いているのはコミュニケーション力・食への関心・向上心がある人
―――では、老健などの高齢者施設での勤務はどんな人に向いていると思いますか?
中田:3つ挙げられるかなと。ひとつは、人と話すことが好きでコミュニケーションが苦にならない人ですね。
栄養管理と一口に言っても、数字だけを見ていればいいものではないです。その人の食事の好みとか性格も理解していないと、その人に合った食事の提供やアドバイスはできません。なので、入所者さんと真摯に向き合えるコミュニケーションスキルはすごく大切ですね。
他職種の人たちと一緒に仕事をする場面も多いので、スタッフとのコミュニケーションも手を抜けませんし、他の人の仕事も理解しておくことも大事です。
ふたつめは、食事に興味がある人だと思います。
イベント食などは力を入れて作るものですが、自分自身が食事に興味がないと苦労すると思います。毎年同じ献立にするならば別ですが。
普段から「日常の食事」というものにアンテナを貼れるか、という部分も大切ですね。何気なく口にしたものを「これ、歯がない入居者にもすすめられるのでは?」と気づいたりとか。
―――3つめはなんでしょうか。
中田:向上心がある人ですね! 私の職場は管理栄養士が私ひとりしかいないので、栄養管理や献立のクオリティなども、すべて私の力量次第なんです。
管理栄養士が複数人いる施設ならまた別だと思いますが、もし就職先が「自分しか管理栄養士がいない」という環境だった場合は、自分がいかに向上心をもってスキルを高めていけるか、にかかっています。
また、栄養学って日々進歩しているので最新知識のアップデートをしなかったり、施設の中に閉じこもっていたりすると、ついていけなくなります。
研修会やセミナーなど管理栄養士同士で情報交換できる機会や場所はあるので、外の世界に出て行って外部の有益な情報を仕入れてくることも大切です。
向上心がある人は学びの姿勢を忘れない人だと思うので、高齢者施設に限らず、専門職には重要だと思います。
老健で仕事を始めたら管理栄養士としての価値観が変わった
―――では最後に、老健で働く管理栄養士としてどんなところにやりがいを感じているか、教えてください。
中田:正直、老健に配属が決まったとき、想定外の場所だったので少し驚きました。
でも実際に働き始めてみると、口から食べることの重要性やありがたさがわかって、管理栄養士として持っておくべき食事の価値観が培われていったり、アップデートされていったりしている点が嬉しいです。
―――食事に対する価値観ですか。
中田:はい。たとえば以前、在宅からうちの施設に入所した人で、食事を全然食べてくれない人がいたんですね。その理由が「自分の家の味と違うから食べられない、美味しいと思えない」というものでした。
それを隣で聞いていたほかの入所者さんが、その人に「そのうち慣れるから大丈夫よ」と返していて、ハッとしました。「家庭によって食事の味って全然違うんだな。慣れるから大丈夫と言っているこの人も、最初はそうだったんだ」と。
こういうふうに、食事に対する気づきが得られたり改めて気づかされたりする出来事が多いところも、老健で働くことの魅力だなと思っています。
―――管理栄養士としての気づきが多い。その経験の蓄積は、中田さんの中で今どんな形になっているんでしょうか。
中田:入所者さんに対する思いかもしれません。入所者さんって、食事を軸に生活しているんです。朝昼晩と2回のおやつの時間に合わせて、部屋から出てきます。つまり、生活の中心が食事なんですよね。
私たちは好きなときに好きなものを食べられる環境にいますが、施設に入っている人たちはそうじゃない。ましてや食事をメインに生活しているので、その食事に不満があると、生活そのものがイヤなものになってしまいかねないんです。
「それだけ入所者さんにとって食事って本当に重要なんだ」と分かってからは、自分の意識も変わっていきました。
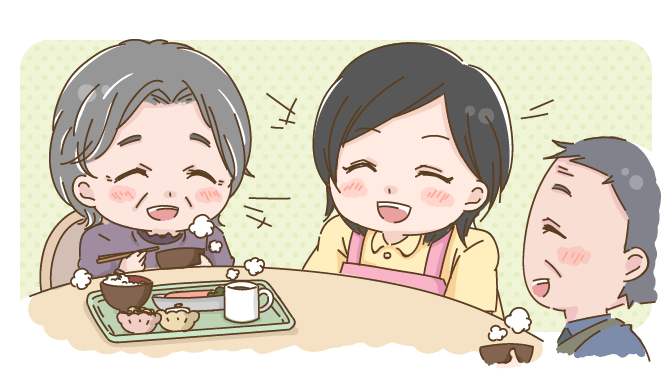
老健などの高齢者施設の入所者さんって、年齢や病気のことを考えると、毎食の食事が誰かの最後の食事になる可能性があります。なので、やっぱり良い気分や思いで食事をしてほしいと考えるようになりました。
そう思いながら仕事をしていると、「美味しかったよ」「今日のイベント食よかったよ」という言葉をもらったり、食べられなかった人が食べられるようになった場面に出くわしたり、私の思いが通じていると思える瞬間にも立ち会えます。
なので、私が感じる老健の管理栄養士のやりがいは、口から食べる幸せを実感でき、その喜びをサポートできるところかなと、思っています。
まとめ
老健をはじめとして、高齢者施設で働く管理栄養士さんたちの話を聞いていると、口から食べることの重要性や食事そのものが入所者さんにとっての毎日の喜びであることを強く意識している人が多い、という印象を受けました。
老健への就職を希望している人たちは、中田さんのように入所者さんの喜びや生活に寄り添える管理栄養士を目指してみてはいかがでしょうか。
栄養士の就職・転職なら「栄養士のお仕事」におまかせ!
栄養士/管理栄養士の転職をサポートする『栄養士のお仕事』にはさまざまな求人情報を掲載しています。
あなたにピッタリの求人や好条件の非公開求人などもあるので、気になる方は下の画像をクリック!
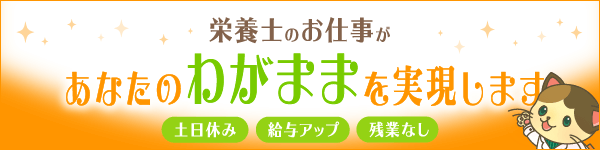
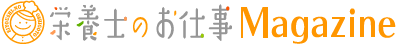

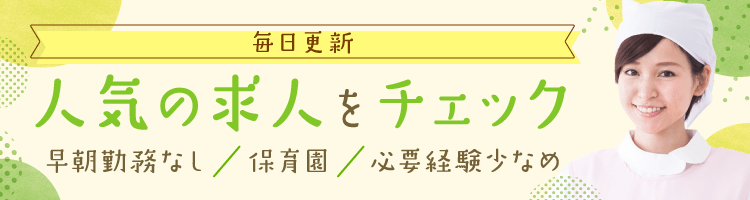
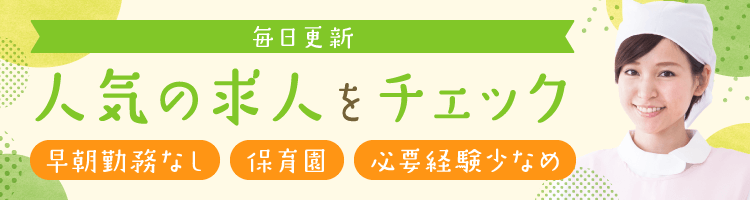





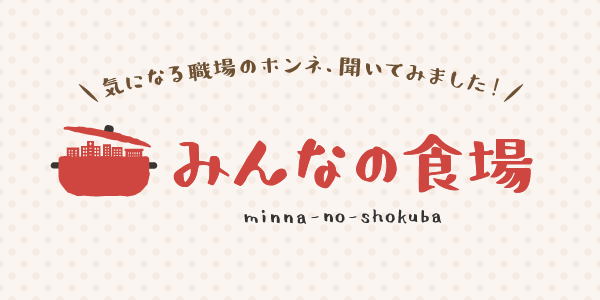 気になる職場のホンネを栄養士さんに聞いてみた!
気になる職場のホンネを栄養士さんに聞いてみた!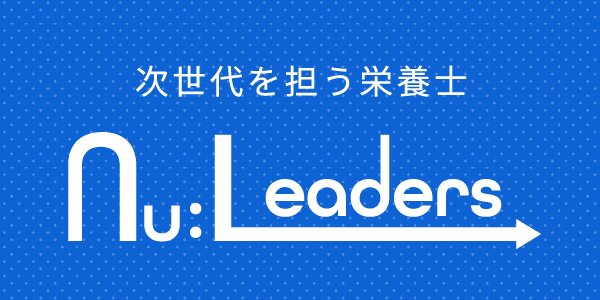 業界の最前線に立つ栄養士さんに直撃インタビュー!
業界の最前線に立つ栄養士さんに直撃インタビュー!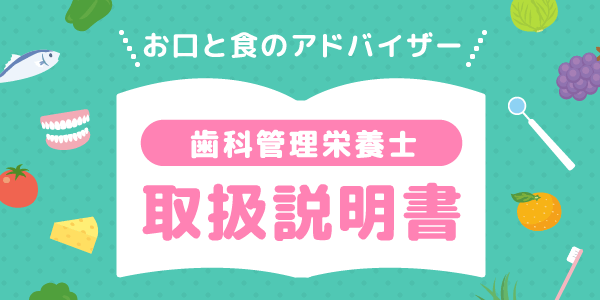 歯科で働く魅力を、現役の管理栄養士がコラム発信☆
歯科で働く魅力を、現役の管理栄養士がコラム発信☆